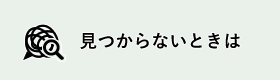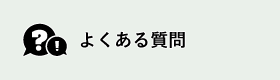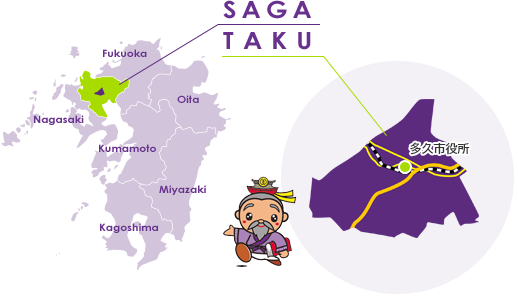国民健康保険税について
国民健康保険とは
この国保の費用を支えているのが、皆さんの納める国民健康保険税(以下「国保税」)や国からの負担金です。国保の円滑な運営を図るため、被保険者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
国保税の納税義務者
※擬制世帯主とは、世帯主が国保の被保険者ではない場合の世帯主のことです。納税義務や届出義務は擬制世帯主が負うことになります。
国保税の計算方法
|
所得割額 (所得のある被保険者ごと) |
均等割額 (一人あたり) |
平等割額 (一世帯あたり) |
賦課限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | (令和6年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×10.94% | 29,800円 | 32,200円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | (令和6年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×3.40% | 9,100円 | 9,100円 | 260,000円 |
|
介護分 (40~64歳の人) |
(令和6年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×2.59% |
12,100円 | 5,300円 | 170,000円 |
・年度途中で加入される場合は、加入された月の分から課税されます。国保に加入する際は届出が必要です。国保税を計算する時期は、届出のタイミングにより変わります。
・年度途中で脱退される場合は、脱退される月の前月分までの課税です。国保を脱退する際は届出が必要です。国保税を計算する時期は、届出のタイミングにより変わります。
・年度途中で40歳を迎えられる方は、40歳になった後に介護分を課税します。届出は不要です。
・年度途中で65歳を迎えられる方は、最初に国保税を課税する際に、65歳になった月からは介護分がかからないように年額の計算をしています。届出は不要です。
・年度途中で75歳を迎えられる方は、最初に国保税を課税する際に、75歳になった月からは国保税がかからないように年額の計算をしています。届出は不要です。
国保税の軽減制度
※軽減対象・軽減額・軽減割合は、法令や条例に基づきます。
※収入がない場合も、世帯主と加入者全員の申告が必要です。
低所得世帯に対する軽減
世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・国保から後期高齢者医療保険に移行した人の前年中の合計所得が一定基準以下の世帯の場合、国保税の均等割額と平等割額の軽減を行っています。軽減を行うための申請は不要です。
| 軽減割合 | 基準となる総所得金額 |
|---|---|
| 2割軽減 | 43万円+(給与所得者等数-1)×10万円+56万円×国保加入者数 以下 |
| 5割軽減 | 43万円+(給与所得者等数-1)×10万円+30.5万円×国保加入者数 以下 |
| 7割軽減 | 43万円+(給与所得者等数-1)×10万円 |
※給与所得者等…一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金等に係る所得がある人(公的年金等収入額が60万円超:65歳未満の人/110万円超:65歳以上の人)
※未申告者がいる世帯に対しては行うことができませんので、前年中の所得がない人でも、市県民税の申告をしてください。
未就学児に対する軽減
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。すでに低所得世帯に対する軽減制度が適用されている場合は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。軽減を行うための申請は不要です。
産前産後の軽減
非自発的失業者に対する軽減
倒産や解雇など会社都合により離職した人には、離職日の翌日から2年度間保険税が軽減される制度があります。この制度は、前年中の給与所得を30/100として保険税を計算します。この制度を利用するためには申請が必要です。
〈対象者〉
離職日に65歳未満で、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知の離職理由コードが次の人
11、12、21、22、23、31、32、33、34
〈申請に必要なもの〉
雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
※特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象外です。
特例対象被保険者(非自発的失業)該当申告書 [PDFファイル/123KB]
【記入例】特例対象被保険者(非自発的失業) [PDFファイル/134KB]
特定同一世帯に対する軽減
75歳になった人が国民健康保険から後期高齢者医療保険制度へ移行することにより、単身となった国保世帯に対して、5年間「医療分」と「支援分」にかかる平等割が2分の1になります。
5年間の軽減措置が終了すると、その後の3年間は「医療分」と「支援分」にかかる平等割が4分の3になります。軽減を行うための申請は不要です。
※この制度が適用されるのは、国保に残る人が一人で、後期高齢者医療制度に移行した人と継続して同一世帯である場合です。世帯主の異動があった場合は同一の世帯とはみなされないため、非該当になります。
国保税の減免制度
地震、大雨、火災等で大きな被害を受けたことにより納税が困難と認められるときは、全部または一部の免除を受けることができる場合があります。この減免を受けるためには申請が必要です。詳しくは保険年金係まで問い合わせください。
災害に遭われた人に対する減免
旧被扶養者に対する減免
社会保険等の被用者保険(※任意継続を含む)の被保険者が75歳に到達して後期高齢者医療保険制度へ移行することに伴い、65歳以上の被扶養者(以下「旧被扶養者」)が国民健康保険に加入される場合は、次のとおり減免措置を行います。減免を行うための申請は不要です。
・旧被扶養者に係る所得割を当面の間賦課しません。
・2年間、旧被扶養者に係る均等割額を半額にする。
・2年間、旧被扶養者のみで国保世帯が構成されている場合は、平等割額を半額にする。
※低所得世帯に対する5割・7割軽減に該当する場合は除きます。
国保税の支払い方法
普通徴収(納付書・口座振替)
●納付書による納付
通年加入の人は6月に、途中加入の人は手続き後に送られる納付書で納付する方法です。佐賀銀行・九州労働金庫・佐賀東信用組合・佐賀県農業協同組合・沖縄県を除く九州内のゆうちょ銀行、全国のコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayB・PayPay)で支払うことができます。
納付期限を過ぎると、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでは支払うことができません。
●口座振替による納付
納期月の末日(12月は25日、土日祝の場合は翌営業日)に指定の口座から振替ます。毎回支払いに行く手間が省けて、納付し忘れることもないため大変便利です。口座振替による納付を希望される人は、手続きが必要です。通帳と届出印を持って、市役所へお越しください。
〈口座振替可能な金融機関〉
佐賀銀行・九州労働金庫・佐賀県農業協同組合・佐賀共栄銀行・佐賀東信用組合・ゆうちょ銀行
〈手続きに必要なもの〉
口座振替可能な金融機関の通帳・通帳の届出印
特別徴収(年金天引き)
特別徴収は、年間6回、受給されている年金がお手元に振り込まれる前に、国保税を天引きさせていただく納付方法です。条件に当てはまる世帯であれば、自動的に特別徴収が始まります。
●特別徴収の対象となる条件
- 国保世帯主と加入者が全員65歳以上である
- 世帯主の介護保険料が引かれる年金の受給額が年間18万円以上
- 世帯主の介護保険料と国保税の合計額が2の年金額の2分の1以下
※国保世帯主が擬制世帯主であるときは、特別徴収されません。
※国保世帯主が年度中(4月から翌年3月まで)に75歳になるときは、特別徴収が中止し普通徴収に変わります。
●特別徴収の人の支払い方法の変更
特別徴収により納付されている人は、届け出をしていただいくことによって、口座振替による納付に変更できます(納付書での納付はできません)。支払い方法の変更を希望される人は、手続きが必要です。ただし、口座振替では確実な納付が見込めない場合は、変更が認められない場合があります。
〈手続きに必要なもの〉
口座振替を希望する金融機関の通帳・通帳の届出印
※振替可能な金融機関は、「口座振替による納付」と同じです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)