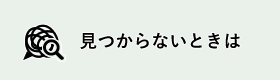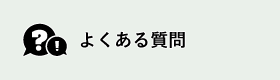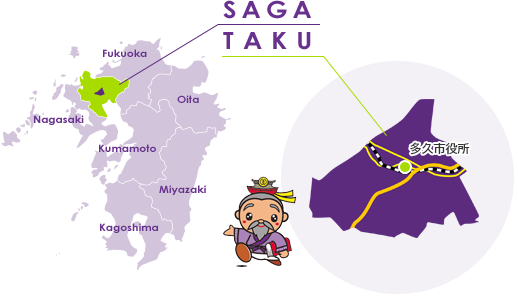特別児童扶養手当
身体や精神に中度以上の障害を有する児童(20歳未満)の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人いに支給されます。
支給制限
・児童や受給の対象となる人が日本国内に住所を有しないとき
・児童が障害を受給理由とする年金を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
・受給資格者本人および扶養義務者の所得制限
・児童が障害を受給理由とする年金を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
・受給資格者本人および扶養義務者の所得制限
支給月額
| 1級該当児童1人につき | 56,800円 |
| 2級該当児童1人につき | 37,830円 |
支給開始
佐賀県知事の認定を受けたあと、認定請求書を提出された日の属する月の翌月分から支給されます。
支給方法
年3回、4月、8月、11月の月の11日に支給されます。
| 期別 | 支給日 | 対象月 |
|---|---|---|
| 4月期 | 4月11日 | 12月、1月、2月、3月 |
| 8月期 | 8月11日 | 4月、5月、6月、7月 |
| 12月期 | 11月11日 | 8月、9月、10月、11月 |
※支給日の11日が金融機関の休業日の場合、その直前の営業日に支給されます。
所得限度額
| 扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 以下213,000円ずつ加算 | ||
| 3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算した額になります。
1.本人の場合は、
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円
2.配偶者および扶養親族の場合は、
・老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
1.本人の場合は、
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円
2.配偶者および扶養親族の場合は、
・老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
手続きに必要なもの
・請求者、対象児童の戸籍謄本 1通(1か月以内に取得したもの)
・住民票謄本(家族全員が載っている本籍・続柄記載のもの)1通
※請求者と対象児童が別居の場合はそれぞれ必要(別居看護申立書も必要)
・診断書(1か月以内に取得したもの)
※診断書を省略できる場合あり
・請求者の口座番号がわかる通帳
・マイナンバーがわかるもの(請求者、配偶者、対象児童)
※生計同一の18歳以上の血族、兄弟姉妹のマイナンバーがわかるものも必要となります。
・住民票謄本(家族全員が載っている本籍・続柄記載のもの)1通
※請求者と対象児童が別居の場合はそれぞれ必要(別居看護申立書も必要)
・診断書(1か月以内に取得したもの)
※診断書を省略できる場合あり
・請求者の口座番号がわかる通帳
・マイナンバーがわかるもの(請求者、配偶者、対象児童)
※生計同一の18歳以上の血族、兄弟姉妹のマイナンバーがわかるものも必要となります。
認定を受けている人の届け出
認定を受けた人は、次の届け出が必要です。
届け出が遅れたり、未提出の場合は、手当の支給が遅くなる・受けられなくなる・手当の返還をすることなどになるため、忘れずに提出ください。
届け出が遅れたり、未提出の場合は、手当の支給が遅くなる・受けられなくなる・手当の返還をすることなどになるため、忘れずに提出ください。
所得状況届
特別児童扶養手当を受給している人は、前年の所得や受給資格等を確認するため、毎年この届け出の提出が必要です。提出されない場合や、所得が所得制限限度額を超える場合は、8月以降の手当が受けられなくなります。
対象者には7月下旬に書類を送付していますので、期限内に提出ください。
対象者には7月下旬に書類を送付していますので、期限内に提出ください。
有期認定更新請求書(再診断)
児童の障害の程度の認定期限の1〜2か月前に案内を通知します。
診断書などを添えて県の再認定を受けます。
この請求を提出しないと手当の受給ができません。
診断書などを添えて県の再認定を受けます。
この請求を提出しないと手当の受給ができません。
受給資格喪失届
受給資格がなくなったとき
児童が障害年金などを受給したとき
児童が施設入所したとき
児童が死亡したとき
児童の監護(養育)を解消したときなど
児童が障害年金などを受給したとき
児童が施設入所したとき
児童が死亡したとき
児童の監護(養育)を解消したときなど
そのほかの届け出
・受給者が死亡したとき(受給者死亡届)
・受給対象者が増えたとき、児童の障害の程度が増進したとき(額改定請求書)
・対象児童が減ったとき、児童の障害の程度が低下したとき(額改定届)
・氏名、住所、振込先金融機関の変更
・受給対象者が増えたとき、児童の障害の程度が増進したとき(額改定請求書)
・対象児童が減ったとき、児童の障害の程度が低下したとき(額改定届)
・氏名、住所、振込先金融機関の変更